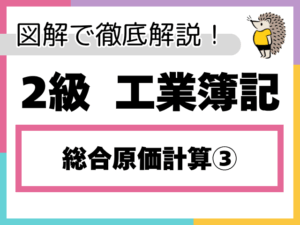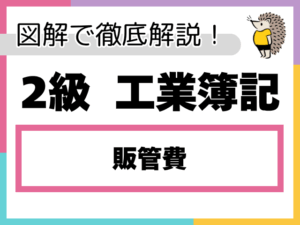はりねずみ
はりねずみ帳簿について、解説していきます!
簿記3級の学習を進めている皆さん、こんにちは!
仕訳や勘定科目の学習は順調でしょうか?
ここまで簿記の一巡についてみてきましたが、実はこれ以外にも学習すべき重要な項目があります。
それが「帳簿(ちょうぼ)」です。
帳簿は、日々の取引を記録し、整理するための非常に大切なツールです。
仕訳を切ることはできるようになっても、それをどこに記録するのか、そして仕訳だけでは得られない詳細な情報をどう管理するのか、といった疑問が出てくるかもしれません。
この記事では、簿記における帳簿の役割と種類、特に主要簿と補助簿について、そして商品有高帳の記入方法に焦点を当てて詳しく解説していきます。
なぜ帳簿が必要なのか?簿記における帳簿の全体像
経理部では、日々の取引を仕訳に起こしますが、この仕訳は「仕訳帳(しわけちょう)」という帳簿に記録されます。
現在の経理実務ではコンピュータへの入力が主流ですが、基本としては仕訳帳に記録するという考え方です。
しかし、仕訳だけでは取引に関する情報が全く足りません。
例えば、売掛金であれば「誰からの売掛金か」「いつ回収期限なのか」といった情報が必要です。
買掛金や固定資産(どんな資産か、耐用年数は何かなど)についても同様です。
仕訳だけでは不十分であり、取引の詳細な内容を記録しておく必要があります。
このように、仕訳や取引情報を記録しておくものを「帳簿」と呼びます。
帳簿は、大きく分けて以下の2種類に分類されます。
主要簿(しゅようぼ)
全ての会社で必ず作成される重要な帳簿。
補助簿(ほじょぼ)
主要簿を補完し、取引の詳細などを記録する帳簿。
必要に応じて作成される。
まずは、これら主要簿と補助簿について、それぞれ具体的に見ていきましょう。
全ての基本となる主要簿:仕訳帳と総勘定元帳
主要簿は2つあります。
1つ目は、先ほども触れた「仕訳帳」です。
これは、日々の取引を仕訳として記入していく帳簿です。
そしてもう1つが「総勘定元帳(そうかんじょうもとちょう)」です。
これは、勘定科目1つ1つの増減を記録していく帳簿です。
ちょうど、勘定科目ごとにTフォームを作成していくイメージです。
総勘定元帳は、1冊の分厚い帳簿をイメージすると分かりやすいかもしれません。
各ページが勘定科目になっており、例えば1ページ目が現金のページ、2ページ目が当座預金のページ、といった形で構成されます。
簿記の基本的な流れとして、まず取引を仕訳に起こし、それを仕訳帳に記入します。
次に、仕訳帳に書かれた情報をもとに、総勘定元帳の該当する勘定科目のページに転記(てんき)という作業を行います。
例えば、商品を掛けで仕入れた場合の仕訳(借方:仕入、貸方:買掛金)であれば、仕訳帳に仕訳を記入した後、総勘定元帳の「仕入」のページには借方に金額と相手勘定科目(買掛金)を、「買掛金」のページには貸方に金額と相手勘定科目(仕入)を記入する、という流れになります。
このように、主要簿である仕訳帳と総勘定元帳は、全ての簿記処理の基礎となる帳簿であり、必ず作成されます。
主要簿を補う補助簿:取引詳細を記録する帳簿
補助簿は、主要簿だけでは不足する取引の詳細な内容や、各勘定科目の増減の内訳などを記録しておくための帳簿です。
仕訳以外の情報が記録されます。
補助簿の種類は非常にたくさんあります。
これは、会社が必要に応じて作成するためです。
補助簿の名称は、法律などで厳密に定められているわけではありませんが、実務上ほぼ事実上決まっていると言ってよいでしょう。
いくつかの代表的な補助簿を挙げていきます。
現金出納帳(げんきんすいとうちょう)
現金の入出金の詳細を記録。
当座預金出納帳(とうざよきんすいとうちょう)
当座預金の増減を記録。
売掛金元帳(うりかけきんもとちょう)
得意先ごとの売掛金の発生と回収を記録。
買掛金元帳(かいかけきんもとちょう)
仕入先ごとの買掛金の発生と支払を記録。
受取手形記入帳(うけとりてがたきにゅうちょう)
受け取った手形に関する詳細を記録。
支払手形記入帳(しはらいてがたきにゅうちょう)
振り出した手形に関する詳細を記録。
商品有高帳(しょうひんありだかちょう)
商品の種類ごとの増減と残高を記録。
固定資産台帳(こていしさんだいちょう)
固定資産の種類、取得価額、減価償却額などを記録。
減価償却計算書を兼ねる場合もある。
仕入帳(しいれちょう)
仕入に関する詳細を記録。
売上帳(うりあげちょう)
売上に関する詳細を記録。
これらの補助簿は、仕訳帳や総勘定元帳を作成した後に必要に応じて作成・記入されます。
商品有高帳:商品の流れを正確に把握するために
補助簿の中でも、簿記3級で特によく学習するのが「商品有高帳」です。
これは、商品の種類ごとに、いつ、何を、いくつ仕入れて(受け入れ)、いつ、何を、いくつ売り出した(払い出し)のか、そして現在の在庫(残高)はいくつあるのかを記録する帳簿です。
商品有高帳を付ける上で特に重要になるのが、「払い出し単価」、つまり売り上げた商品の仕入れ値(売上原価)をいくらとするかという問題です。
同じ商品でも、仕入れた時期によって単価が異なる場合があるためです。
この払い出し単価の計算方法には、主に以下の2つの方法があります。
先入先出法(さきいれさきだしほう)
これは、先に仕入れた商品から順に売り出されると考える方法です。
仕入れ値が異なる場合は、それぞれの単価ごとに分けて記録しておき、払い出しがあった際は古い単価の商品から払い出したものとして記録します。
例えば、100円で300個仕入れたあと、110円で700個仕入れた場合、商品有高帳の残高欄には「100円×300個」「110円×700個」のように分けて記入します。
そのあと、400個売り出した場合、払い出し欄にはまず先に仕入れた100円の商品から300個、次に残りの100個は110円の商品から払い出した、として記入します。
残高は、110円の商品が600個残ったことになります。
移動平均法(いどうへいきんほう)
これは、商品を仕入れる都度、その時点での平均単価を計算し直し、その新しい平均単価で払い出しを評価する方法です。
先入先出法のように仕入れ値ごとに分けて記録せず、同じ種類の商品は混ぜて記録します。
例えば、100円で300個(合計30,000円)仕入れたあと、110円で700個(合計77,000円)仕入れた場合、合計1,000個の仕入れ金額は107,000円(30,000円+77,000円)となります。
この時点で、商品の平均単価は107円(107,000円 ÷ 1,000個)と計算されます。そのあと400個売り出した場合、払い出し単価はこの移動平均単価である107円を使用します。
先入先出法と移動平均法は、どちらの方法も認められています。
ただし、一度採用した評価方法は、原則として継続して適用しなければならないというルールがあります。
まとめ
帳簿は、簿記における取引の記録・管理の要です。
主要簿である仕訳帳と総勘定元帳は全ての会社で必ず作成され、補助簿は主要簿を補完し詳細な情報を記録するために必要に応じて作成されます。
特に商品有高帳は、商品の増減を記録するだけでなく、売上原価を計算するための基礎となる払い出し単価の計算が重要です。
先入先出法と移動平均法の違いをしっかり理解しておきましょう。
帳簿の作成方法や記入ルールは、簿記3級の試験でも問われる重要な論点です。
テキストなどで具体的な記入例を繰り返し練習し、理解を深めていくことをお勧めします。
この解説が、皆さんの簿記3級合格に向けた学習の一助となれば幸いです。
頑張ってください!