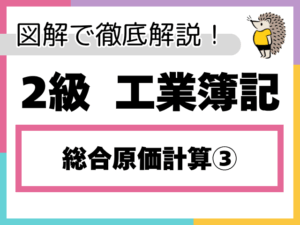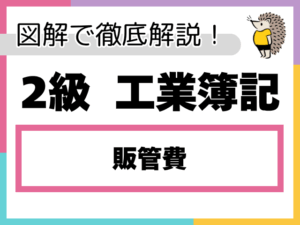はりねずみ
はりねずみ伝票について、解説していきます!
簿記3級の学習を進めている皆さん、こんにちは!
独学での合格を目指す上で、避けては通れない論点の1つに「伝票(でんぴょう)」があります。
伝票は、日々の取引を記録するための非常に重要な書類です。
今回の記事では、簿記3級で学習する伝票について、その基本的な役割から具体的な使い方、そして独学でつまずきやすい応用的な起票方法まで、詳しく解説していきます。
伝票をマスターして、簿記3級合格へ一歩近づきましょう!
簿記における「伝票」とは?
簿記では、日々の取引を記録することが非常に大切です。
この記録は「仕訳(しわけ)」という形で表現されます。
そして、この仕訳をどこに書くのかというと、それが「伝票」です。
伝票の役割と仕訳帳との関係性
以前の学習では、仕訳は「仕訳帳(しわけちょう)」に記載されると学びました。
しかし、今回は、仕訳は伝票に記載されると解説しています。
これはどういうことでしょうか?
実は、伝票は仕訳帳の代わりとして用いられることがあるのです。
つまり、仕訳を仕訳帳に書くこともあれば、もし伝票を用いるのであれば、伝票に記載するということになります。
伝票を用いない場合は、仕訳帳に書きます。仕訳を記録するという点では、伝票も仕訳帳も同じ役割を果たすと言えます。
伝票は、いわば仕訳帳の代わりなのです。
伝票から総勘定元帳への流れ
伝票に記載された仕訳の情報は、最終的に「総勘定元帳(そうかんじょうもとちょう)」に転記されます。
伝票は、仕訳帳の代わりとなるため、伝票に書かれた仕訳の情報が総勘定元帳に1つ1つ転記されることになります。
この転記の方法にはいくつかのパターンがあります。
1つ目は、伝票に記載された仕訳情報を1つ1つ個別に総勘定元帳に転記する方法です。
2つ目は、1日分の各勘定科目の合計値を一旦集計し、その合計値を総勘定元帳に転記する方法です。
この集計を行う帳票を「仕訳日計表(しわけにっけいひょう)」と呼びます。
仕訳日計表から総勘定元帳へ合計値を転記することを「合計転記(ごうけいてんき)」と言うこともあります。
このように、伝票は仕訳帳の代わりとして、日々の取引の仕訳を記録し、総勘定元帳へ情報を伝える役割を担っています。
簿記3級で必須!「三伝票制」を理解しよう!
実務では様々な種類の伝票が使われますが、試験で学習するのは主に3種類の伝票です。
これを「三伝票制(さんでんぴょうせい)」と呼んでいます。
三伝票制の種類と基本的な使い分け
三伝票制で使用される伝票は、以下の3種類です。
- 振替伝票(ふりかえでんぴょう)
- 入金伝票(にゅうきんでんぴょう)
- 出金伝票(しゅっきんでんぴょう)
これらの伝票は、取引の内容によって使い分けられます。
基本的な使い分けは以下の通りです。
振替伝票
入出金(現金を受け取ったり支払ったりする取引)以外の取引で使います。
言い換えれば、仕訳の借方または貸方のどちらか一方でも現金ではない場合に使う伝票です。
それ以外の全ての場合に振替伝票を使います。
入金伝票
入金取引で使います。
これは、仕訳の借方が現金となる場合に使う伝票です。
出金伝票
出金取引で使います。
これは、仕訳の貸方が現金となる場合に使う伝票です。
なぜこのように使い分けるのでしょうか?
実は、基本となるのは振替伝票です。
実務でも振替伝票(一般会計伝票などと呼ばれることも)しか使わない企業も多いです。
しかし、入金や出金の取引が毎日たくさんある場合、いちいち「(借方)現金」や「(貸方)現金」と仕訳を書くのが非常に面倒になります。
そこで、あらかじめ借方が現金であると分かっている入金伝票や、あらかじめ貸方が現金であると分かっている出金伝票を使うことで、効率化を図るのです。
振替伝票に入金伝票や出金伝票が加わることで、三伝票制となります。
入金伝票を使った仕訳では、必ず借方が現金となりま。
同様に、出金伝票を使った仕訳では、必ず貸方が現金となります。
この性質から、入金伝票や出金伝票では、「借方:現金」や「貸方:現金」といった記述は省略されることが一般的です。
伝票にはあらかじめ印字されているか、あるいは何も書かないことで現金であることを示しています。
したがって、これらの伝票に書くのは、主に相手の勘定科目と金額、そして日付などになります。
ケース別!伝票の具体的な起票例と応用
それでは、いくつかの取引を例に、どの伝票を使ってどのように起票するのかを見ていきましょう。
例1
受取利息500円を現金で受け取った。
この取引の仕訳は、以下の通りです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 現金 | 500 | 受取利息 | 500 |
借方が現金なので、使う伝票は入金伝票です。
入金伝票には相手勘定科目と金額を書けば良いので、相手勘定科目に「受取利息」、金額に「800」と記載します。
例2
電気代5,000円を現金で支払った。
この取引の仕訳は、以下の通りです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 水道光熱費 | 5,000 | 現金 | 5,000 |
貸方が現金なので、使う伝票は出金伝票です。
出金伝票には相手勘定科目と金額を書けば良いので、相手勘定科目に「電気代」、金額に「10,000」と記載します。
貸方の現金は書かれません。
例3
電気代5,000円を小切手を振り出して支払った。
この取引の仕訳は、以下の通りです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 水道光熱費 | 5,000 | 当座預金 | 5,000 |
この仕訳には現金が出てきません。
現金が登場しない取引では、振替伝票を使います。
振替伝票には、通常の仕訳と同じように「(借方)電気代 10,000 / (貸方)当座預金 10,000」と記載します。
例4
商品10,000円を掛けで仕入れた。
この取引の仕訳は、以下の通りです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 仕入 | 10,000 | 買掛金 | 10,000 |
これも現金が出てこない取引なので、振替伝票を使います。
振替伝票には、通常の仕訳と同じように「(借方)仕入 100,000 / (貸方)買掛金 100,000」と記載します。
例5
商品10,000円を現金で仕入れた。
この取引の仕訳は、以下の通りです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 仕入 | 10,000 | 現金 | 10,000 |
貸方が現金なので、使う伝票は出金伝票です。
出金伝票には相手勘定科目と金額を書くので、相手勘定科目に「仕入」、金額に「100,000」と記載します。
例6
商品10,000円を仕入れ、代金のうち3,000円は現金で支払い、残額は掛けとした。
この取引の仕訳は、以下の通りです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 仕入 | 10,000 | 現金 買掛金 | 3,000 7,000 |
この取引には現金による支払い(出金)が含まれていますね。
この取引に対する伝票の起票方法は、2種類あります。
1つ目は、取引を分解して考える方法です。
まず、
| 借方 | 貸方 | ||
| 仕入 | 7,000 | 買掛金 | 7,000 |
を振替伝票で起票します。
次に、
| 借方 | 貸方 | ||
| 仕入 | 3,000 | 現金 | 3,000 |
を出金伝票で起票します。
出金伝票には相手勘定科目に「仕入」、金額に「20,000」と書きます。
2つ目は、元の仕訳を分解しない方法です。
まず、取引全体の仕入額100,000円を
| 借方 | 貸方 | ||
| 仕入 | 10,000 | 買掛金 | 10,000 |
として振替伝票で起票します。
次に、支払った現金3,000円について、
| 借方 | 貸方 | ||
| 買掛金 | 3,000 | 現金 | 3,000 |
という
「買掛金20,000円を現金で支払った」
として出金伝票で起票します。
出金伝票には、相手勘定科目に「買掛金」、金額に「20,000」と書きます。
結果として、
| 借方 | 貸方 | ||
| 仕入 | 10,000 | 現金 買掛金 | 3,000 7,000 |
となり、元の仕訳と同じになります。
この2つ目の方法は、1つ目の方法に比べて面倒に感じるかもしれませんが、どちらも試験に出る可能性があります。
いずれの取引でも起票できるようにしておきましょう。
まとめ
今回の記事では、簿記3級で学習する伝票について解説しました。
伝票は日々の取引を仕訳として記録し、総勘定元帳へつなぐ重要な役割を持っています。
特に、三伝票制(振替伝票、入金伝票、出金伝票)については、それぞれの基本的な使い方だけでなく、現金を含む複雑な取引に対する応用的な起票方法(特に仕訳を分解しない方法)を理解し、練習することが簿記3級合格のためには非常に有効です。
伝票の理解を深めるためには、たくさんの問題を解くことが1番です。
ぜひ、練習問題を活用して理解度を確認してみてください。
伝票の問題は、最初は難しく感じるかもしれませんが、仕組みを理解し、パターンに慣れてしまえば必ず解けるようになります。
自分のペースで、1つずつ確実にマスターしていきましょう。
応援しています!