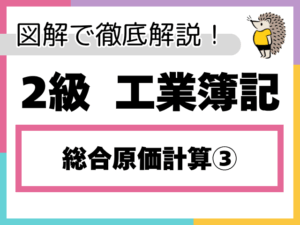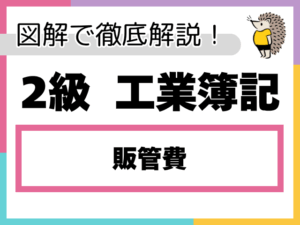はりねずみ
はりねずみ剰余金の配当について、解説していきます!
簿記3級の学習を進めている皆さん、こんにちは!
今回は簿記3級の学習の中でも、少しイメージが掴みにくいかもしれない「剰余金の配当」について、わかりやすく解説していきます。
決算が終わってホッと一息…と思いきや、会社の経理にはまだやることがあります。
そう、「株主総会」を開き、利益の処分方法などを決めるのです。
そこで登場するのが「剰余金の配当」や「利益準備金」といった項目です。
えば、株主総会でこんな決議がされたとしましょう。
株主総会で繰越利益剰余金300万円について、次のように決議された。
- 配当金は100万円とする。
- 利益準備金を10万円積み立てる。
- 残額は次回の剰余金の処分まで繰り越す。
「繰越利益剰余金」とは、過去に稼いだ利益のうち、会社内にため込まれた金額の累計額のことです。
このたまった利益をどうするかを、株主総会で決めるのですね。
さあ、この決議内容、簿記ではどのように処理するのでしょうか?一緒に見ていきましょう!
剰余金の配当って何?まずは全体像を知ろう
剰余金の配当とは、簡単に言うと会社が株主に対して、利益の一部を分配することです。
一般的には「配当金の支払い」と呼ばれます。
会社法ではこの行為を「剰余金の配当」と呼ぶのですね。
では、配当金は具体的に何を支払うのでしょうか?
それは現金です。
株主へは、配当金領収証が送られて金融機関で現金に換えられる場合もあれば、銀行振込で直接支払われる場合もあります。
どちらにしても、会社から現金が流出することになります。
株主総会ってどんなところ?
剰余金の配当を決めるのは、「株主総会」です。
株主総会とは、会社の所有者である株主が集まる会議のことです。
会社組織のピラミッド構造で言うと、株主総会は一番上に位置し、社長よりも偉い存在です。
株主総会で決められたことは、社長でも覆すことができません。
株主総会は、会社の最高意思決定機関として、会社にとって最も重要な事項を決定します。
具体的には、以下のようなことを決めます。
決算の承認
会社が作成した財務諸表が正しいかどうかを承認します。
会社の合併や解散
役員の選任や解任
社長をクビにするかどうかなどもここで決まります
配当金の支払い
株主総会は、最低でも年に1回必ず開催されます。
通常は決算期末(3月末)の後、中小企業であれば5月下旬、上場企業であれば6月下旬に開催されることが多いようです。
配当金支払いの仕訳をマスター!
それでは、先ほどの株主総会での決議例を使って、簿記の仕訳を見ていきましょう。
- 配当金は100万円とする。
- 利益準備金を10万円積み立てる。
- 残額は次回の剰余金の処分まで繰り越す。
まず、「配当金は100万円とする」という決議に対する仕訳です。株主総会で配当を決議しても、その日のうちにすぐに現金を支払うケースは少ないです。
そのため、決議日にはまだ支払っていない金額として処理します。
未払いの配当金には、「未払配当金」という勘定科目を使います。これは負債の勘定科目です。
| 借方 | 貸方 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,000,000 | 未払配当金 | 1,000,000 |
「繰越利益剰余金」は、資本(純資産)の勘定科目です。
今回は、これが減っているため、ホームポジションの反対側である借方(左側)に記入します。
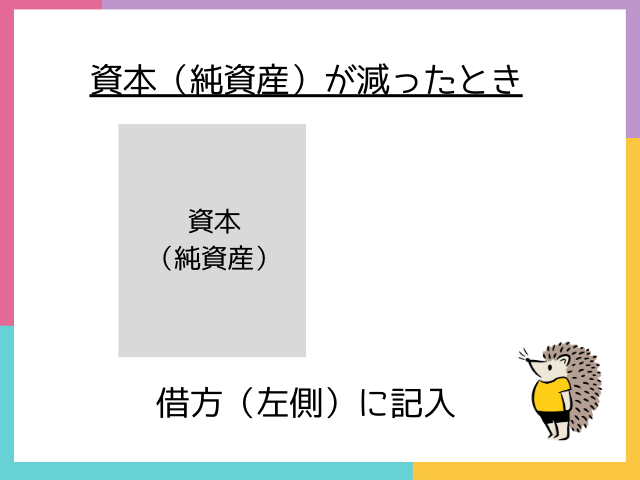
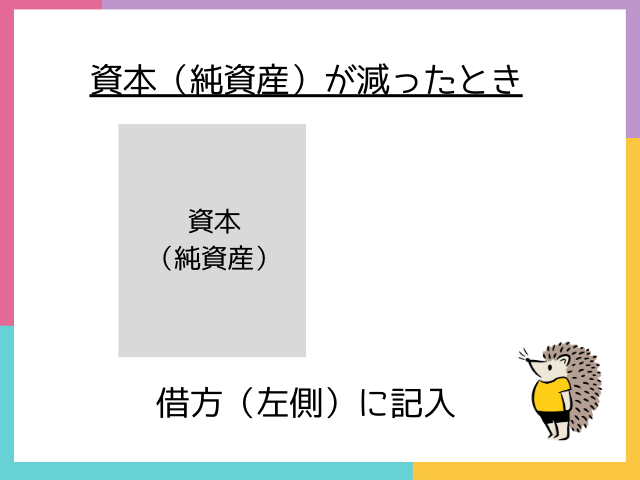


「未払配当金」は、負債の勘定科目です。
今回は、これが増えているため、ホームポジションである貸方(右側)に記入します。
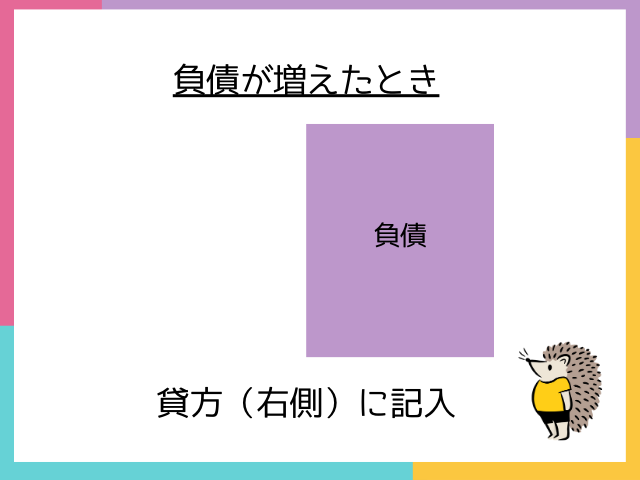
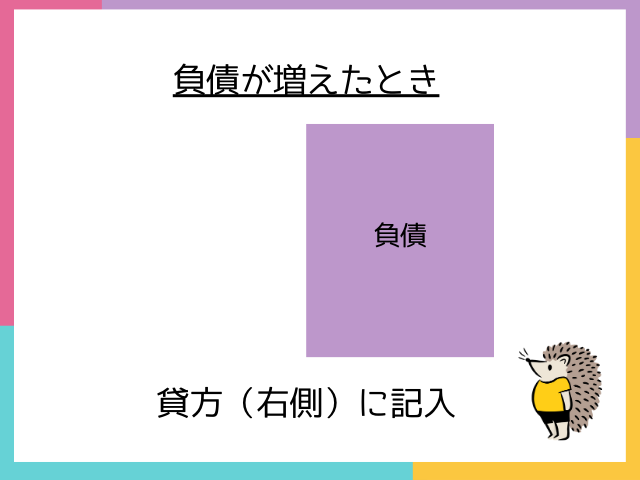


この仕訳の意味は、
「配当金として100万円を支払うことを決議したので(まだ払ってないけど)、その分、繰越利益剰余金を減らします」
ということです。
後日、実際に配当金を支払った時(通常は銀行振込など)は、以下の仕訳になります。
| 借方 | 貸方 | ||
| 未払配当金 | 1,000,000 | 普通預金 | 1,000,000 |
「未払配当金」は、負債の勘定科目です。
今回は、これが減っているため、ホームポジションの反対側である借方(左側)に記入します。
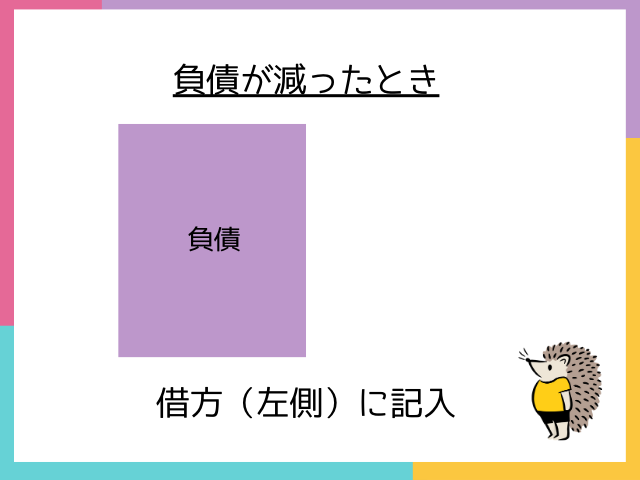
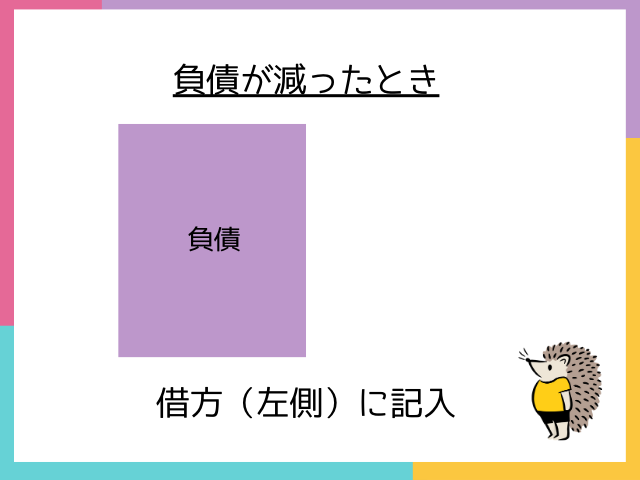


「普通預金」は、資産の勘定科目です。
今回は、これが減っているため、ホームポジションと反対側である貸方(右側)に記入します。
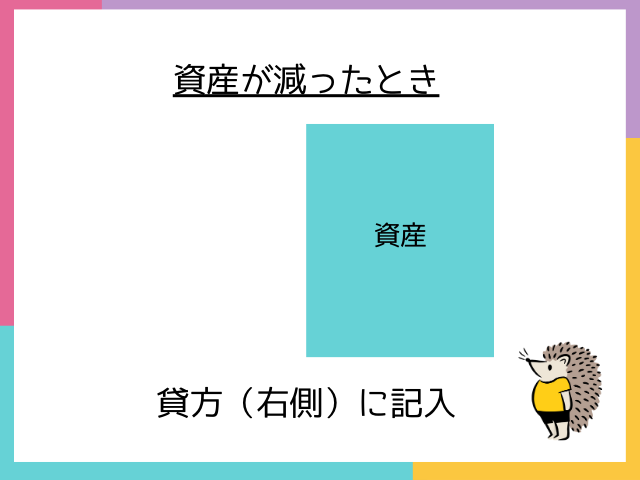
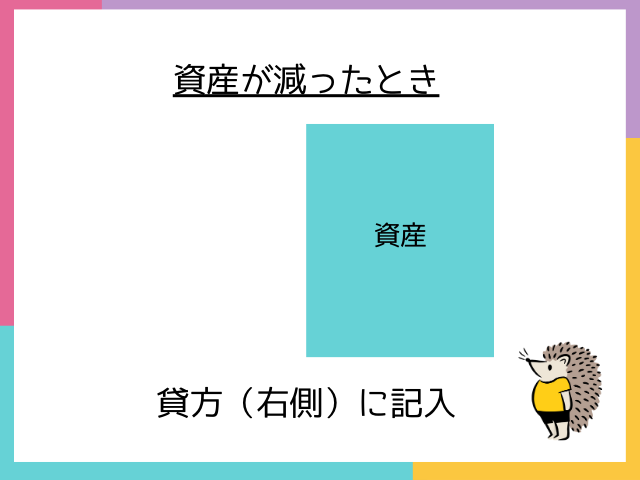


これは、
「未払配当金という負債がなくなった代わりに、現金が100万円減りました」
という意味ですね。
繰越利益剰余金が減る理由
配当金を支払う(決議する)ときに、なぜ「繰越利益剰余金」を減らすのでしょうか?
「繰越利益剰余金」は、これまでに稼いで会社に蓄積された利益の集まりでしたね。
会社法的な考え方では、この溜まった利益の中から配当を支払う、というイメージになります。
しかし、簿記的に仕訳を読み解くと、配当金の支払い(または支払いの約束)という現金(または将来現金になるもの)の流出に伴って、資本(純資産)の項目である繰越利益剰余金を減らすという処理になるのです。
配当を出すから繰越利益剰余金が減る、というよりは、現金の支払いという事象を処理するために、純資産の代表である繰越利益剰余金を減らす、という仕訳の構造になっています。
【補足:源泉所得税について】
会社が株主に配当金を支払う際には、「源泉徴収」という手続きが必要です。
これは、会社が株主の所得税や住民税をあらかじめ差し引いて(預かって)、後で税務署などに納める義務を負うというものです。
例えば、配当金100万円に対して20万円(所得税15万円、住民税5万円の合計とします)を源泉徴収する場合、株主には80万円だけを支払い、残りの20万円は会社が預かっておき、後で納付します。
この場合、決議時の仕訳は少し変わります。預かった税金は「預り金」という勘定科目(負債)で処理します。
| 借方 | 貸方 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,000,000 | 未払配当金 預り金 | 800,000 200,000 |
「繰越利益剰余金」は、資本(純資産)の勘定科目です。
今回は、これが減っているため、ホームポジションの反対側である借方(左側)に記入します。
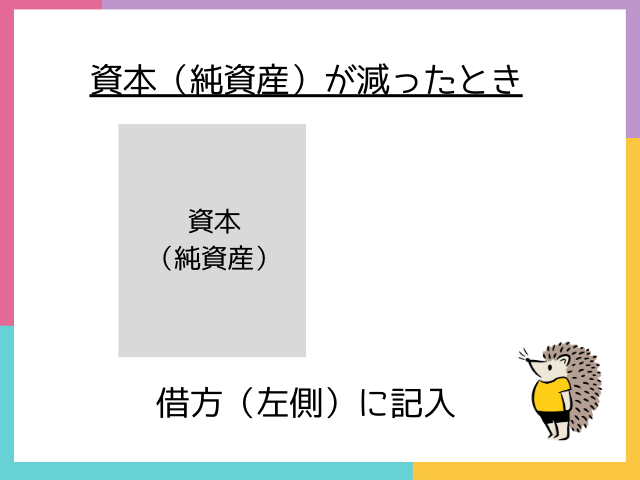
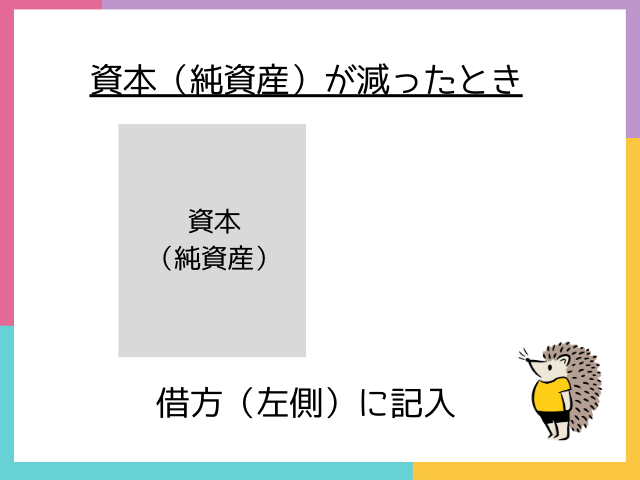


「未払配当金」は、負債の勘定科目です。
今回は、これが増えているため、ホームポジションである貸方(右側)に記入します。
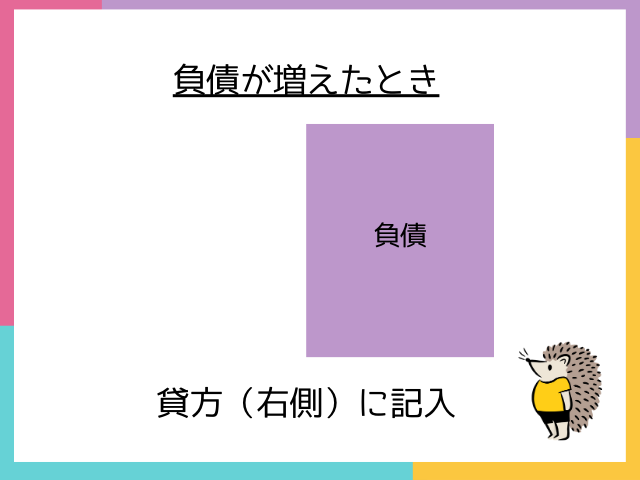
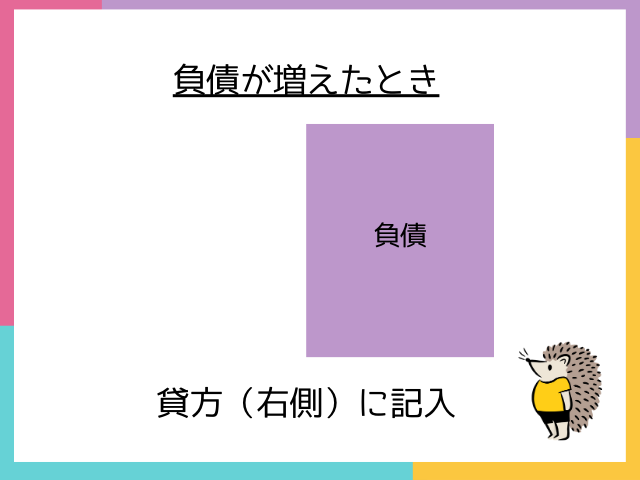


「預り金」は、負債の勘定科目です。
今回は、これが増えているため、ホームポジションである貸方(右側)に記入します。
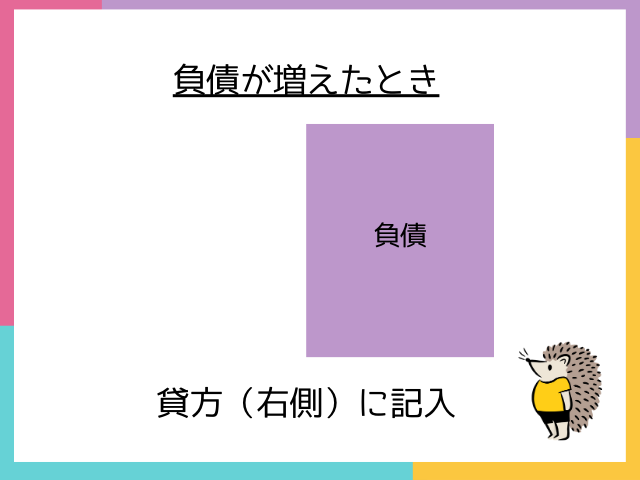
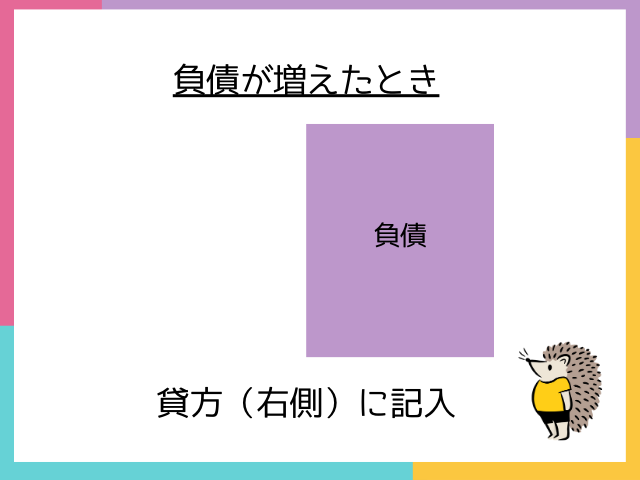


繰越利益剰余金は100万円全額減らしますが、未払配当金(株主へ直接支払う分)は80万円となり、差し引いた20万円は預り金(後で税務署等へ納める分)となります。
後日、株主へ配当金(手取り80万円)を支払い、税務署へ源泉徴収税額(20万円)を納付した時の仕訳は以下のようになります。
| 借方 | 貸方 | ||
| 未払配当金 預り金 | 800,000 200,000 | 普通預金 | 1,000,000 |
「未払配当金」は、負債の勘定科目です。
今回は、これが減っているため、ホームポジションの反対側である借方(左側)に記入します。
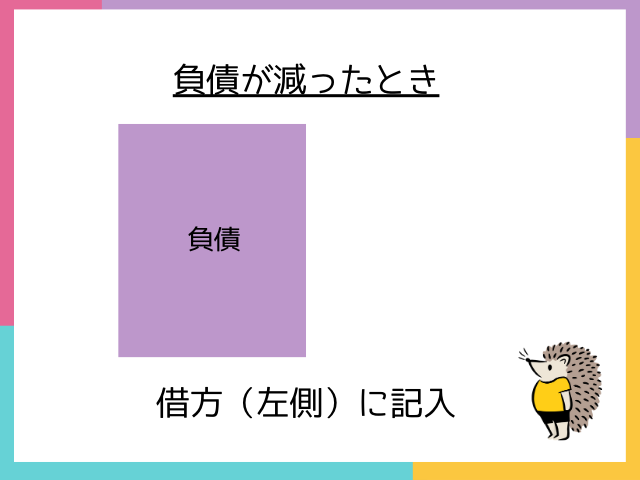
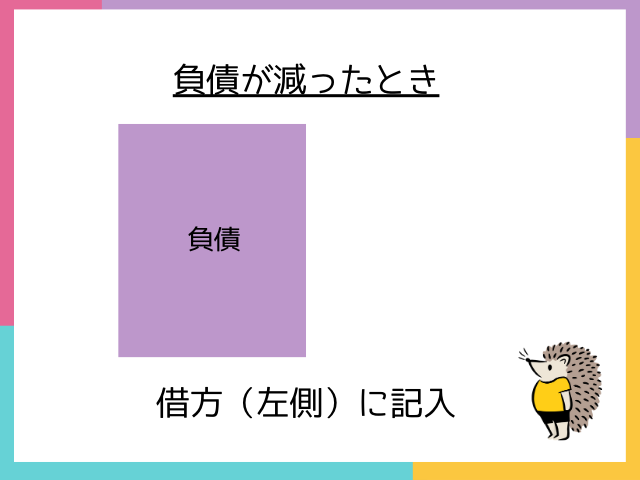


「預り金」は、負債の勘定科目です。
今回は、これが減っているため、ホームポジションの反対側である借方(左側)に記入します。
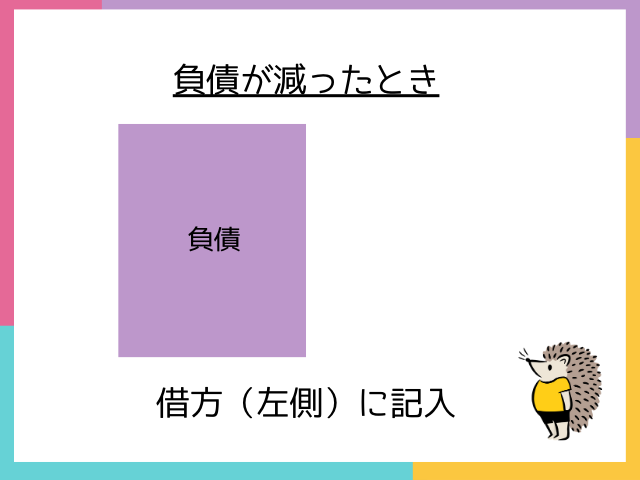
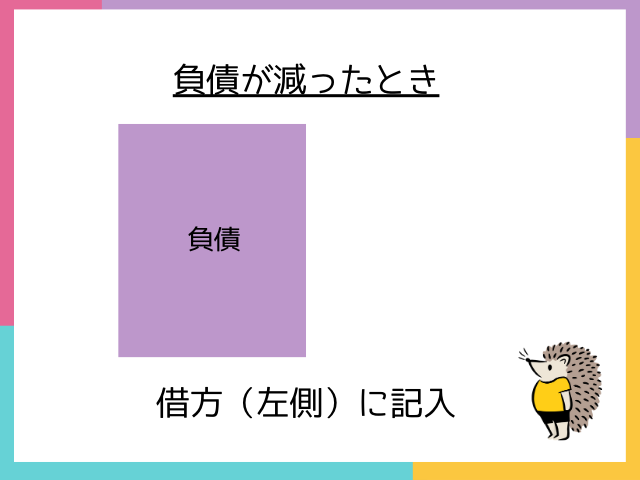


「普通預金」は、資産の勘定科目です。
今回は、これが減っているため、ホームポジションと反対側である貸方(右側)に記入します。
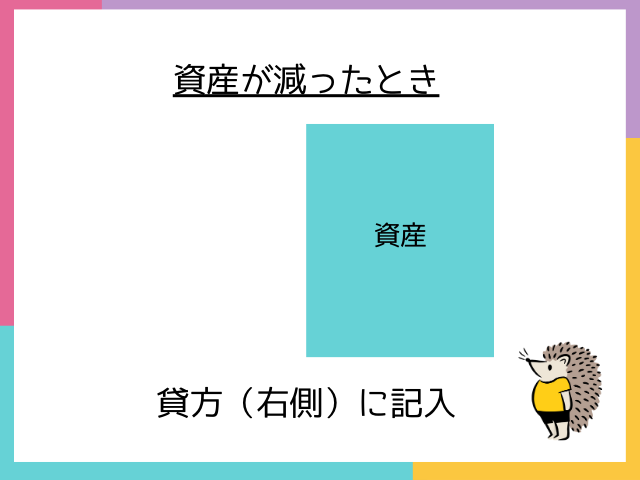
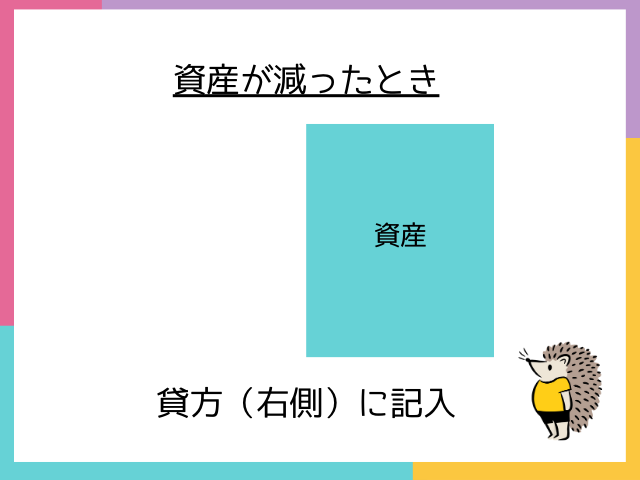


支払日と納付日が異なる場合は、仕訳を分けます。
上記は、同日に現金で処理した場合の例です。
利益準備金の意味と仕訳
さて、株主総会の決議内容には、もう一つ「利益準備金」という項目がありました。
利益準備金を10万円積み立てる。
「利益準備金」とは何でしょうか?
これも「繰越利益剰余金」と同じ、資本(純資産)の勘定科目です。
そして、この「積み立てる」という言葉が、少しイメージと違うかもしれません。
「積み立てる」のイメージにご注意!
「利益準備金10万円を積み立てる」と聞くと、どこかの銀行口座に10万円を貯金する、あるいは会社のお金を別の場所に取っておく、というイメージを持つかもしれません。
しかし、これは実際にお金を積み立てる(現金をどこかによけておく)という意味ではありません。
簿記上で行う処理は、以下の仕訳です。
| 借方 | 貸方 | ||
| 繰越利益剰余金 | 100,000 | 利益準備金 | 100,000 |
「繰越利益剰余金」は、資本(純資産)の勘定科目です。
今回は、これが減っているため、ホームポジションの反対側である借方(左側)に記入します。
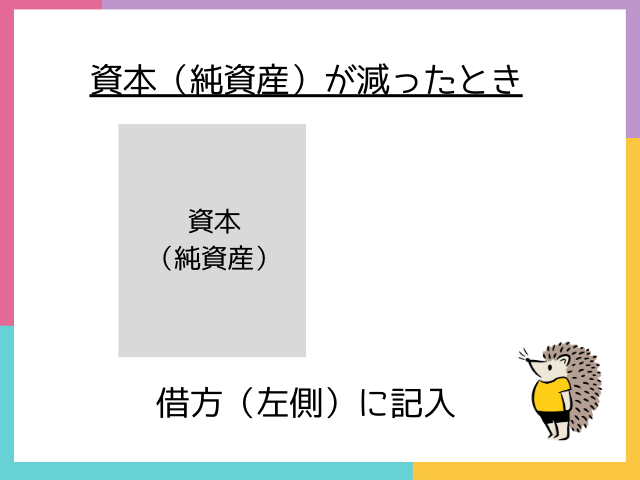
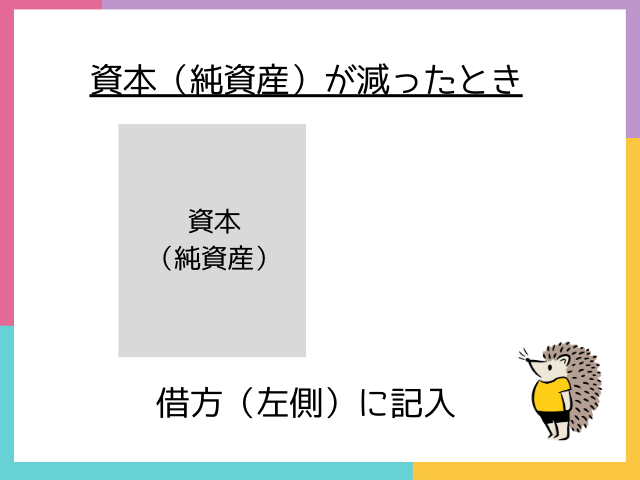


「利益準備金」は、資本(純資産)の勘定科目です。
今回は、これが増えているため、ホームポジションである貸方(右側)に記入します。
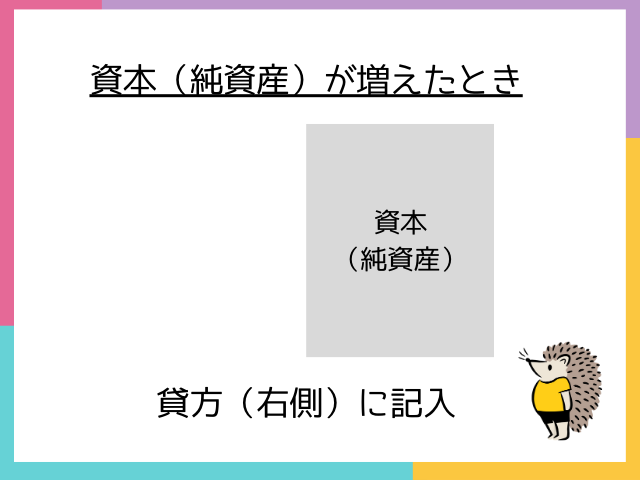
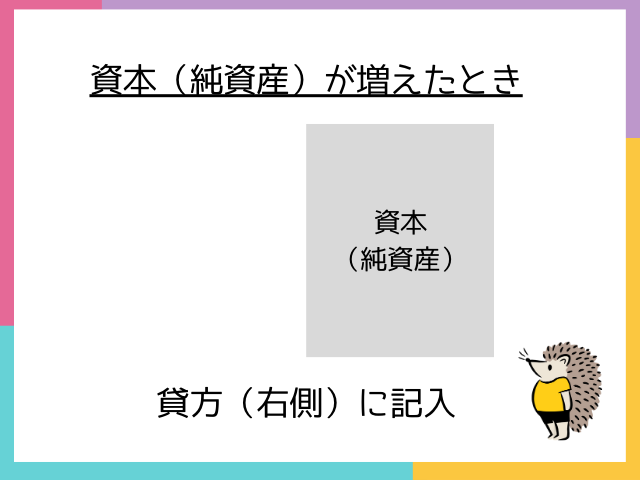


この仕訳は、
「繰越利益剰余金という名前だった純資産の一部を、利益準備金という名前に変更しました」
という意味なのです。
つまり、純資産の中での勘定科目の名前を付け替えただけで、会社のお金(現金など)が実際に増減したわけではありません。
では、なぜこんな「積み立てる」という言葉を使って、名前を付け替えるような処理をするのでしょうか?
これは、会社法によって定められているルールだからです。
会社法では、株主に配当を行う場合、その配当額の10分の1を「利益準備金」として積み立てなさい(繰越利益剰余金から利益準備金へ振り替えなさい)、と決められています。
このルールは、会社の財務基盤を強化したり、いざという時のために会社にお金を残しておくことで、債権者などを保護したりする目的があると考えられます。
会社法が「こうすべきだ」と言っているから、そのルールに従って仕訳を行う、ということなのですね。
まとめ
今回の「剰余金の配当」の学習は、株主総会での決議、配当金の支払い、そして利益準備金の積み立てという一連の流れを簿記でどう処理するかを理解することが重要です。
最終的な決議内容(配当金100万円、利益準備金10万円積み立て、残額繰り越し)を、未払配当金と利益準備金を使う場合の仕訳でまとめると、以下のようになります。
これは、源泉所得税を考慮しない単純な例です。
| 借方 | 貸方 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,100,000 | 未払配当金 利益準備金 | 1,000,000 100,000 |
「繰越利益剰余金」は、資本(純資産)の勘定科目です。
今回は、これが減っているため、ホームポジションの反対側である借方(左側)に記入します。
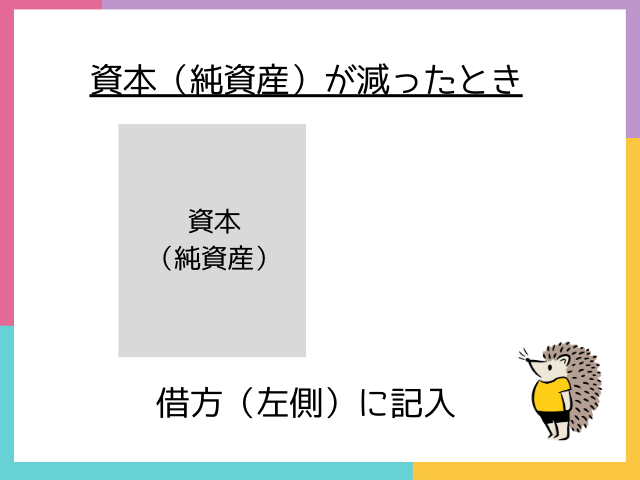
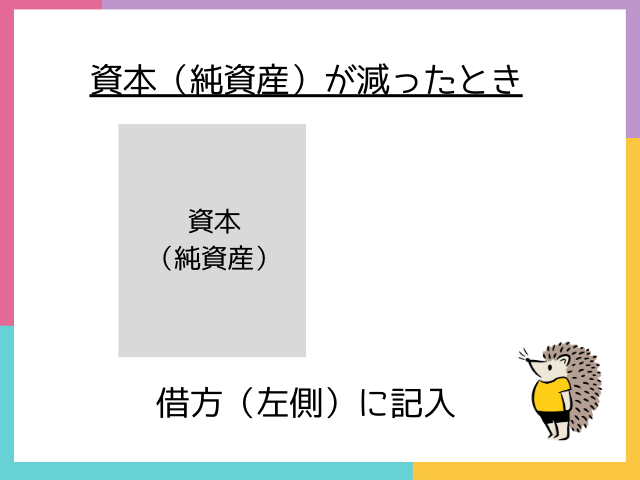


「未払配当金」は、負債の勘定科目です。
今回は、これが増えているため、ホームポジションである貸方(右側)に記入します。
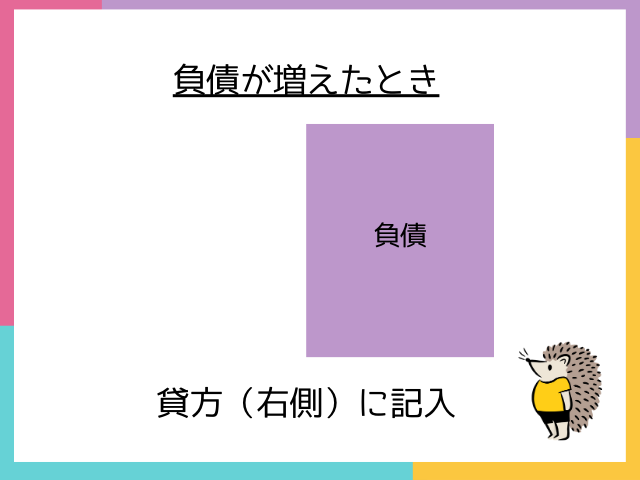
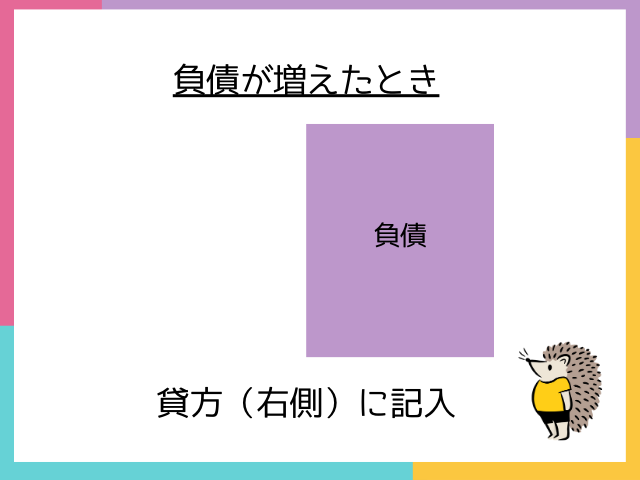


「利益準備金」は、資本(純資産)の勘定科目です。
今回は、これが増えているため、ホームポジションである貸方(右側)に記入します。
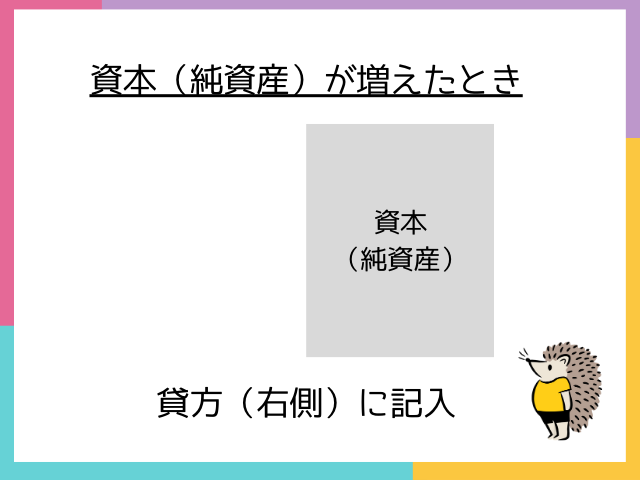
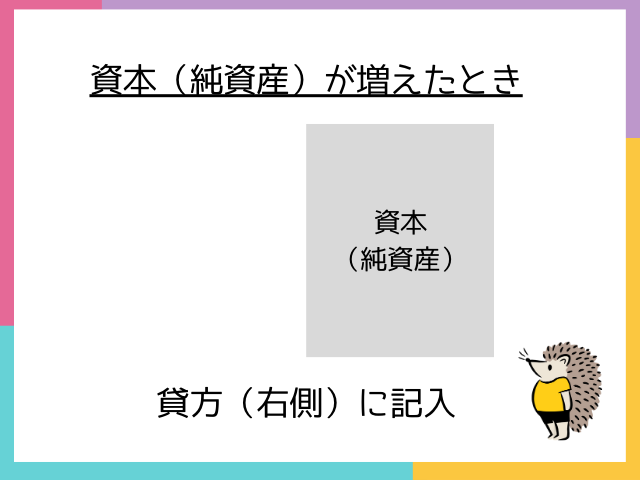


この仕訳は、
「繰越利益剰余金の中から、配当金として100万円を後で払うことにし、利益準備金として10万円を確保することに決めたので、合計110万円分、繰越利益剰余金を減らしました」
という意味合いになります。
「剰余金の配当」に関するこれらの仕訳は、貸借対照表の「純資産の部」の変動として非常に重要です。
そして、今回の内容をもって、簿記の一巡、つまり期首から期末、そして決算・株主総会・納税までの一通りの流れを簿記的に理解するための基礎が整ったことになります。
仕訳自体は比較的シンプルなので、まずは形をしっかり覚えましょう。
その上で、なぜこの仕訳になるのか、株主総会での決議がどういう意味を持つのか、利益準備金とは何か、といった背景を理解することで、より深く簿記の知識を定着させることができます。
簿記3級合格に向けて、引き続き頑張ってください!