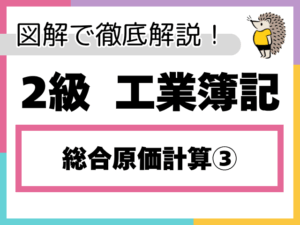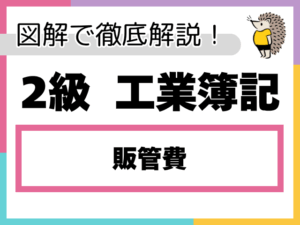はりねずみ
はりねずみ決算の学習を進めていくにあたり、まずは全体観をつかんでいきましょう。
簿記3級の学習を進める上で、「決算」は多くの受験生が重要視する、まさに簿記の集大成とも言える部分です。
独学で合格を目指すなら、この決算の全体像をしっかりと把握することが非常に重要になります。
ここでは、提供された動画の解説に基づき、決算とは何か、なぜ行うのか、そしてどのような流れで行われるのかを分かりやすく解説します。
簿記3級の重要論点!「決算」とは何か?
会社を「区切る」作業、それが決算
決算日と「期」の考え方
多くの日本企業では、4月1日から翌年3月31日までの1年間を「一期」として区切っています。
この区切られた期間を、最初の期間から順に「第1期」「第2期」「第3期」…と呼んでいきます。
なぜ決算が必要なのか?その目的とは?
日々の取引は「仕訳」として帳簿に記録されますが、これらの膨大な仕訳をただ記録しただけでは、会社の状況は把握できません。
そこで、決算という区切りを設けることで、集計作業を行い、会社の成績表や財産状況一覧を作成するのです。
決算で作成する主要な「財務諸表」(BSとPL)を理解しよう!
決算のゴールは、「財務諸表」の作成
簿記3級の試験でも、この財務諸表を作成する問題が必ず出題されます。
財務諸表はいくつか種類がありますが、特に重要なのは次の2つです。
会社の財産状況を示す「貸借対照表(BS)」
貸借対照表は、決算日(期末)という「ある時点」における会社の「財政状態」を示す表です。
具体的には、会社が持っている財産である「資産」、将来支払う義務のある「負債」、そして資産から負債を差し引いた株主の持ち分である「純資産」がいくらあるのか、またどのようなものがあるのかを表します。
これは、ある時点の状態を示す情報であり、「ストック」の情報と呼ばれます。
会社の儲けを示す「損益計算書(PL)」
損益計算書は、決算によって区切られた「ある期間」(通常1年間)の会社の「経営成績」を示す表です。
具体的には、その期間に会社が得た収入である「収益」と、事業を行う上でかかった支出である「費用」を集計し、収益の合計から費用の合計を差し引くことで、その期間に会社がいくら儲かったのか(または損失が出たのか)を示す「当期純利益(または当期純損失)」を計算します。
これは、ある期間の活動結果を示す情報であり、「フロー」の情報と呼ばれます。
BSとPLのつながり
決算作業の具体的なステップと「試算表」の役割
日々の仕訳は財務諸表作成のため
期中仕訳を集計した「試算表(TB)」とは?
試算表は、ある時点までに作成された全ての仕訳を、勘定科目ごとに集計した表です。
例えば、特定の時点での現金の借方取引の合計と貸方取引の合計を集計し、その差額である残高を一覧にしたようなものです。
仕訳は必ず借方と貸方の金額が一致するため、その仕訳を集計した試算表も、借方合計と貸方合計は必ず一致します(貸借一致)。
試算表は、経理の実務では毎月作成されることが多く、経営状況の分析などにも利用されます。
決算の具体的なステップ:前TB、後TB、そして財務諸表へ
決算作業は、主に以下のステップで進められます。
決算日までの日々の仕訳(期中仕訳)を全て集計し、その時点での「決算整理前試算表」(前TB)を作成します。
これは、決算整理を行う前の現時点での集計結果を示しています。
決算日になったら、決算期末でしか行わない特別な仕訳を作成します。
これを後述する「決算整理仕訳」と呼びます。
作成した決算整理仕訳を、前TBの集計結果に織り込んで再集計します。
これにより、「決算整理後試算表」(後TB)が完成します。
後TBは、決算整理を全て終えた最終的な集計結果を示しています。
完成した後TBをもとに、貸借対照表(BS)と損益計算書(PL)を作成します。
イメージとしては、後TBの上半分にある勘定科目(資産、負債、純資産など)を使ってBSを、下半分にある勘定科目(費用、収益など)を使ってPLを作成するような形です。
簿記3級で学ぶ必須知識!「決算整理仕訳」
決算期末に行う特別な仕訳
例えば、三分法という商品売買の記帳方法では、期中仕訳だけでは期間の利益が計算できないため、決算整理仕訳でこれを算出します。
簿記3級で学ぶ決算整理仕訳の種類
これらの決算整理仕訳は、正確な当期純利益や期末の財政状態を計算するために不可欠なものです。
減価償却費の計上、貸倒引当金の設定、費用や収益の繰延べ・見越し、棚卸資産の評価などがこれに該当します。
これら一つ一つの決算整理仕訳の内容と処理方法を理解することが、簿記3級合格には必須となります。
学習のポイント(税金処理など)
決算整理仕訳を学習する際は、いきなり全てを詰め込むのではなく、段階的に進めるのがおすすめです。
まず、消費税や法人税等といった「税金のない世界」での基本的な決算整理処理を理解し、その上で税金に関連する決算整理仕訳(法人税等の処理など)を学習していく流れで学習していきましょう。
これは、税金処理が加わると利益計算などが少し複雑になるため、まずは税金のない世界で決算処理の一巡をマスターしてから、税金を含むケースを学ぶ方が分かりやすいからです。
まとめ
簿記3級の「決算」は、日々の仕訳を集計し、会社の「経営成績」(PL)と「財政状態」(BS)という財務諸表を作成するための、年に一度の重要な手続きです。
決算作業では、期中仕訳の集計結果である「試算表」を使い、さらに「決算整理仕訳」という特別な仕訳を加えて調整することで、正確な財務諸表を完成させます。
特に、簿記3級で学ぶ10種類程度の決算整理仕訳は、1つ1つを丁寧に理解することが、合格への鍵となります。
決算の全体像をしっかり把握し、各ステップの意味を理解しながら学習を進めましょう。
応援しています!