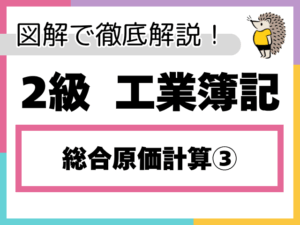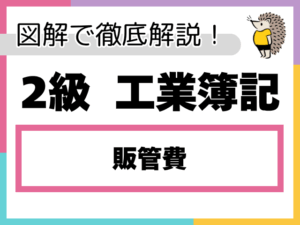はりねずみ
はりねずみ精算表について、解説していきます!
簿記の学習は、日々の取引を記録する「仕訳」から始まり、最終的に企業の成績や状態をまとめる「決算」へと進みます。
特に、決算手続きの中で作成される「精算表」は、簿記3級の試験において非常に重要な論点であり、これをマスターすることが合格への鍵です。
精算表は一見複雑そうに見えますが、実はその作り方は驚くほど簡単です。
独学で合格を目指す方は、まず簿記の全体像を掴み、最も基本的な「仕訳」を確実に身につけることから始めましょう。
この記事では、簿記の基本的な流れから精算表、そして精算表作成の土台となる「仕訳」の重要性までを解説します。
簿記の基本の流れと決算の重要性
企業の経済活動は、まず取引が発生し、それを「仕訳」として記録することから始まります。
この仕訳は会計期間中(例えば1年間)継続して行われます。
会計期間の終わりには「決算」が行われ、期間中の取引を集計し、企業の経営成績(利益が出たのか損失が出たのか)と期末時点での財政状態(どのような資産や負債、資本があるのか)を明らかにします。
決算の最初のステップは、期中の仕訳を集計した「決算整理前試算表」の作成です。
しかし、これだけでは正しい状態を示すことができません。
期末には、例えば売掛金に対する貸倒引当金の設定、在庫として残っている商品の評価、建物などの固定資産の減価償却、まだ支払っていない費用(未払費用)の計上など、「決算整理仕訳」を行う必要があります。
これらの決算整理仕訳によって数値を調整し、「決算整理後試算表」を作成します。
簿記の学習において、この決算整理仕訳の正確な理解と習得は極めて重要です。
簿記3級の核!精算表の作り方をマスターする
簡単なのに苦手意識を持たれやすい理由
簿記3級の試験対策として、多くの人が「精算表」の学習に取り組みます。
精算表は、決算整理前試算表に決算整理仕訳を反映させ、損益計算書と貸借対照表を作成するための一覧表です。
通常、「勘定科目」「試算表」「修正記入」「損益計算書」「貸借対照表」といった列で構成されています。
精算表の作り方は、試算表(決算整理前試算表)の数値に修正記入(決算整理仕訳)の増減を加減し、その結果を損益計算書項目か貸借対照表項目かに振り分けて記載するという、いたってシンプルな作業の繰り返しです。
例えば、期中に発生した現金過不足5円(借方)を決算で原因不明として雑損に振り替える決算整理仕訳を行った場合、
| 借方 | 貸方 | ||
| 雑損 | 5 | 現金過不足 | 5 |
精算表の「修正記入」列の雑損の行の借方に5、現金過不足の行の貸方に5と記載します。
そして、「試算表」列の現金過不足の数値5と修正記入欄の数値5を加減した最終結果0を、対応する「損益計算書」列か「貸借対照表」列に記入します(この場合は残高ゼロなので何も記入しません)。
売上(試算表3,000)のような収益の勘定科目は「損益計算書」列の貸方に、仕入(試算表2000+修正記入借方300-修正記入貸方200=2100)のような費用の勘定科目は「損益計算書」列の借方に、現金(試算表150)のような資産は「貸借対照表」列の借方に記入していきます。
精算表の最後の行では、収益と費用の差額として当期純利益(または損失)を計算し、これを損益計算書列と貸借対照表列の差額として記入することで、両列の合計が一致するように仕上げます。
これだけ聞くと簡単そうに思える精算表ですが、多くの勘定科目や複数の決算整理仕訳が登場する問題 を解くと、全体の流れが見えにくくなり、苦手意識を持ってしまう人がいるようです。
しかし、基本的な構造と作成手順を理解すれば、精算表は本当に簡単なのだと分かります。
まずは、勘定科目や決算整理仕訳が少ないシンプルな例題で、精算表の全体の流れを掴んでみましょう。
精算表から財務諸表へ、そして仕訳の力
完成した精算表の「損益計算書」列と「貸借対照表」列の情報を使えば、正式な財務諸表である損益計算書と貸借対照表を簡単に作成できます。
損益計算書は収益と費用、そして当期純利益(損失)を表示し、企業の一定期間の経営成績を示します。
貸借対照表は資産、負債、純資産を表示し、企業の期末時点の財政状態を示します。
財務諸表を作成する際には、精算表の勘定科目名とは異なる表示名を使用することがあります。
例えば、精算表の「繰越商品」は貸借対照表では「商品」となり、「売上」は損益計算書で「売上高」となります。
また、貸倒引当金や減価償却累計額といった特定の項目は、負債ではなく関連する資産の価値から差し引く形で、資産の部にマイナスとして表示されるというルールもあります。
実際には、元の資産価額と減価償却累計額等を並記し、差額を表示する形式が一般的です。
精算表の作成、そして財務諸表の作成は、どれもその前提として正確な決算整理仕訳ができていることが不可欠です。
仕訳が簿記の全ての出発点であり、最も重要な要素です。
独学で簿記3級を目指すなら、まずは基本的な仕訳、そして決算整理仕訳のパターンを徹底的に練習しましょう。
仕訳の力がつけば、精算表も財務諸表もきっと理解できるようになります。
精算表は決して難しいものではありません。
仕訳の力を味方につけて、簿記3級合格を目指していきましょう!