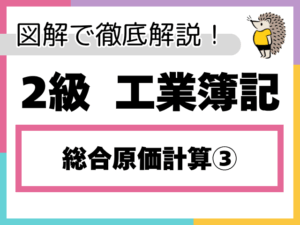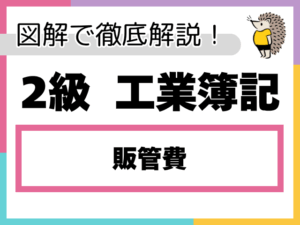はりねずみ
はりねずみ証憑について、解説していきます!
仕訳のルールや勘定科目を覚えるのは大変ですが、実務ではこれらの知識をどのように活かすのでしょうか?
簿記の学習では、通常「問題文」として与えられた文章を基に仕訳を行います。
例えば、「出張から帰社した社員が電車代5万円を支払い、報告を受けたため、同社員に現金で支払った」という文章を見て、「旅費交通費 50,000 / 現金 50,000」と仕訳を切る、といった具合です。
しかし、実際の会社の経理部では、文章だけを見て仕訳をすることはありません。
では、何を基に仕訳を行うのでしょうか?
それが、今回のテーマである「証憑(しょうひょう)」です。
仕訳に不可欠な「証憑」とは?その種類と具体例
証憑とは、仕訳の元となる資料やデータのことを指します。
これを「原始証憑」とも呼ぶことがあります。
経理担当者は、これらの証憑を確認し、それに書かれている内容を読み取って仕訳を行います。
証憑は多岐にわたりますが、簿記3級の学習で特によく目にする代表的なものをいくつか見ていきましょう。
領収書・レシート
最も身近な証憑の一つが領収書です。
これは、何かにお金を支払った際に受け取るものですね。
スーパーやコンビニなどでは、領収書とは言わずに「レシート」と呼ぶことが一般的ですが、税法上の解釈はさておき、レシートもお金を支払った証拠となります。
むしろ、最近では領収書よりもレシートの方が取引の詳細(品目など)が分かりやすいため、良いとされる場合も少なくありません。
経費の支払いや商品の代金支払いなどで現金や小切手、手形を渡した場合に、必ず相手から受け取るべきものです。
なお、金額によっては領収書に収入印紙を貼る必要がありますが、これは通常、領収書を作成する側(お金を受け取る側)が行います。
納品書・請求書
商品を仕入れたり販売したりする際に出てくるのが、納品書や請求書です。
商品を仕入れた場合、商品と一緒に納品書が送られてくるのが一般的です。
これは仕入先が発行したものですね。
その後、請求書が送られてきたり、納品書と請求書が一体になった「納品書兼請求書」という形である場合もあります。
商品を販売した側からすると、納品したという証拠が必要になります。
この場合、納品書を2枚作成し、商品を渡した相手にサインや押印をもらって控えを持ち帰ることで、相手が確かに商品を受け取ったこと、つまり自社が商品を販売したことの証憑となります。
この控えを「受領書」と呼ぶこともあります。
預金通帳・取引照会(入出金データ)
銀行を介した取引、特に普通預金や当座預金からの支払いまたは入金があった場合の証憑としては、預金通帳や銀行からの取引明細、そしてオンラインバンキングによる入出金データ(取引照会)があります。
普通預金であれば、通帳を記帳すればいつ、いくら出金または入金があったかを確認できます。
最近の当座預金などでは通帳がない場合も多く、その場合は会社のパソコンからオンラインで銀行にアクセスし、入出金情報を画面上で確認したり、銀行から定期的に送られてくる取引明細を確認したりして、仕訳を行います。
これらのデータは、預金口座を経由した取引の確実な証拠となります。
具体例で学ぶ!「証憑」から仕訳を読み解く実践練習
では、実際の証憑を見て、どのように仕訳に結びつけるのか、いくつか例を見ていきましょう。
例1
A社から商品(パソコン5台、合計150万円)を掛けで仕入れた。
相手先から「納品書兼請求書」を受け取ります。
この証憑には、仕入れた日付、仕入先、品名、数量、金額、そして支払期日などが記載されています。
これを見て、「商品150万円を掛けで仕入れた」と判断し、以下の仕訳を行います。
| 借方 | 貸方 | ||
| 仕入 | 1,500,000 | 買掛金 | 1,500,000 |
例2
例1で発生した買掛金150万円を後日現金で支払った。
代金を支払うと、相手先から「領収書」を受け取ります。
領収書には、支払った日付、金額、宛名(自社名)、そして「現金」で受け取った旨がチェックされているなどが記載されています。
この領収書を確認して、以下の仕訳を行います。
| 借方 | 貸方 | ||
| 買掛金 | 1,500,000 | 現金 | 1,500,000 |
例3
例1で発生した買掛金150万円を当座預金からの振り込みで支払った。
この場合、先方から領収書は受け取りません。
この場合は、オンラインバンキングの入出金データ(取引照会)などで、当座預金口座から300万円が出金された記録を確認します。
例えば、7月31日にオンラインで確認した画面で、7月30日に300万円の出金があったことが表示されていれば、それが証憑となります。
これを見て、以下の仕訳を行います。
| 借方 | 貸方 | ||
| 買掛金 | 1,500,000 | 当座預金 | 1,500,000 |
例4
B社へ商品100万円を掛けで販売した。
自社が発行した納品書の控え(相手の受領サイン入りなど)が証憑となります。
これには販売した日付、販売先、品名、数量、金額などが記載されており、100万円で販売したことが読み取れます。
これを見て、以下の仕訳を行います。
| 借方 | 貸方 | ||
| 売掛金 | 1,000,000 | 売上 | 1,000,000 |
例5
例4の売掛金100万円をB社振出の小切手で回収した。
この場合、受け取った小切手そのものが証憑となります。
小切手には、振出人(B社)、金額(100万円)などが記載されています。
他人振出小切手は受け取った時点で現金として扱われるため、以下の仕訳を行います。
| 借方 | 貸方 | ||
| 現金 | 1,000,000 | 売掛金 | 1,000,000 |
例6
取引先への商談で発生した駐車料金700円を営業担当者が立て替え、後日経理部が本人に現金で精算した。
この場合、営業担当者から駐車場の「領収書」を受け取ります。
領収書には、支払った日付、金額(600円)、支払先、そして内容(駐車料金など)が記載されています。
この領収書を見て、以下の仕訳を行います。
| 借方 | 貸方 | ||
| 旅費交通費 | 700 | 現金 | 700 |
これらの例からもわかるように、様々な取引が、それぞれの証憑と結びついています。
仕訳を正確に行うためには、これらの証憑を正しく読み取る力が必要不可欠です。
「証憑」は仕訳のためだけじゃない?もう一つの重要な役割
ここまで、証憑が仕訳の「元」となる資料であると説明してきました。
しかし、証憑にはもう一つ非常に重要な役割があります。
それは、「エビデンス(証拠)」としての役割です。
会社の経理は、定期的に税務署による税務調査や、上場企業などでは会計監査人による会計監査を受けます。
これらの調査や監査では、会社が作成した帳簿や計算書類が正しいかどうかを厳しくチェックされます。
その際、「この仕訳は本当に正しいのか?」「この取引は実際に行われたのか?」といった疑問に対して、証憑を提示して証明する必要があります。
領収書、契約書、銀行の入出金明細など、様々な証憑が、取引の事実や金額、内容が正確であることを示す「証拠」となるのです。
そのため、証憑は仕訳を行うためだけでなく、税務調査や会計監査に備えて、決められた期間(通常は法人税法や会社法で定められた期間)きちんと整理して保管しておくことが非常に重要です。
証憑がなければ、たとえ実際に行った取引であっても、それを証明することが難しくなってしまいます。
まとめ
簿記3級の学習では、問題文から仕訳を考える練習が中心ですが、実務では証憑を見て仕訳を切るのが基本です。
そして、その証憑は単なる仕訳の元データであるだけでなく、会社の取引が正確に行われたことを証明する「証拠」としての役割も果たします。
独学で簿記3級合格を目指す皆さんにとって、仕訳の正確さは非常に重要です。
問題演習を通じて、様々な取引に対応する仕訳を覚えることはもちろん大切ですが、その仕訳がどのような証憑に基づいているのか、実際の証憑にはどのような情報が記載されているのかをイメージできるようになると、より深く簿記を理解できるはずです。
今回の内容を参考に、仕訳と証憑の関係性をしっかり押さえて、簿記3級合格へ向けて頑張ってください!