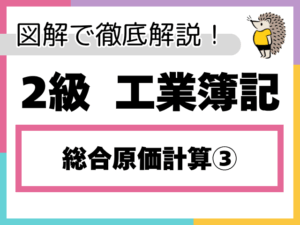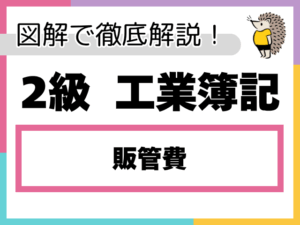はりねずみ
はりねずみ部門別個別原価計算について、基礎から解説していきます!
これ以外にも、日商簿記3級に独学合格を目指す方のための解説記事を多数掲載しています。
ぜひ、あわせてご確認ください。


【復習】個別原価計算とは?


部門別個別原価計算とは?
\ ここがポイント!/
そもそも、原価って何だったっけ…?
広告代
営業を担当する従業員の給料
などの「販売費」や
本社建物の減価償却費
などの会社を管理・運営するためにかかった「一般管理費」なども含まれます。
製品の製造にかかった金額の総額が「製造原価」です。
なお、この製造原価に
- 販売費
- 一般管理費
を含めた金額を「総原価」といいます。
製造原価を分類すると…
木製の家具をつくっている会社を例に、それぞれを見てみましょう。
材料費とは?
労務費とは?
経費とは?
部門別個別原価計算とは?
ここからがこの記事のメインテーマです。
製造直接費に分類される
- 直接材料費
- 直接労務費
- 直接経費
は、どの製品にいくらかかったのかが明確ですね。
そのため、原価を部門別にとらえる必要はなく、そのまま各製造指示書に賦課されます。
(製造直接費を製造指示書ごとに集計することを「賦課(ふか)」といいます。)
一方、製造間接費は、どの製品にいくらかかったのかが明確ではありません。
そのため、直接作業時間などの配賦基準にもとづいて、各製造指示書に配賦する必要があります。
(「配賦(はいふ)」とは、割り当てることです。)
工場の規模が大きくなってくると、製造を担当するのが1つの部署だけでない場合が増えてきます。
木製の家具をつくっている会社であれば、
- 木を伐採して、工場に運ぶ部門
- 木材を加工する部門
- 加工した木材を組み立てる部門
- 出来上がった製品を店舗に運ぶ部門
- 修繕を担当する部門
- 事務を担当する部門
などのイメージです。
これらの部門は、発生する製造間接費の内容も金額も違ってきますね。
そのため、すべての製造間接費を直接作業時間などの1つの配賦基準で配賦すると、原価の計算を正確に行うことができません。
より正確に原価を計算するための手段が、部門別個別原価計算です。
部門別に製造間接費を集計し、それぞれの部門に適した配賦基準で各製造指示書に配賦します。
部門個別費と部門共通費
部門個別費とは?
特定の部門固有のもののため、該当部門に直接賦課します。
部門共通費とは?
複数の部門で発生するもののため、適切な配賦基準によって、それぞれの部門に配賦します。
部門個別費と部門共通費の集計


部門個別費は、
| A部門 | B部門 | C部門 | |
| 部門個別費 | 100 | 200 | 300 |
ですね。
部門共有費は、
- 建物減価賞費 → 占有面積
- 電気代 → 使用電力量
を配賦基準として、各部門に配賦してみましょう。
建物減価償却費の配賦基準は、
1,000円 ÷ 100㎡ = @10円
です。
これを各部門の占有面積に当てはめると、
【A部門】
@10円 × 20㎡ = 200円
【B部門】
@10円 × 30㎡ = 300円
【C部門】
@10円 × 50㎡ = 500円
ですね。
また、電気代の配賦基準は、
100円 ÷ 50kWh = @2円
です。
これを各部門の使用電力量に当てはめると、
【A部門】
@2円 × 5kWh = 10円
【B部門】
@2円 × 15kWh = 30円
【C部門】
@2円 × 30kWh = 60円
です。
これをまとめると、
製造間接費部門別配賦表
(単位:円)
| 配賦基準 | 合計 | A部門 | B部門 | C部門 | |
| 部門個別費 | 600 | 100 | 200 | 300 | |
| 部門共通費 | |||||
| ∟ 建物減価償却費 | 占有面積 | 1,000 | 200 | 300 | 500 |
| ∟ 電気代 | 使用電力量 | 100 | 10 | 30 | 60 |
| 部門費 | 1,700 | 310 | 530 | 860 |
となります。
補助部門費を製造部門に配賦するときは、どう処理する?
補助部門費とは?
部門ごとの製造間接費を集計したら、補助部門費(補助部門に集計された製造間接費の合計額)を製造部門に配賦します。
この補助部門費の製造部門への配賦方法には、
- 直接配賦法
- 相互配賦法
の2種類があります。
直接配賦法による補助部門費の配賦
事務部門は、製造部門の従業員の分だけでなく、補助部門である修繕部門の従業員の給与計算もしていますね。
補助部門は製造部門だけでなく、ほかの補助部門に対してもサービスを提供しているということです。
直接配賦法では、この補助部門間のサービスのやり取りを無視します。
製造間接費部門別配賦表
(単位:円)
| 合計 | A部門 | B部門 | C部門 | |
| 製造部門 | 製造部門 | 補助部門 | ||
| 部門個別費 | 600 | 200 | 300 | 100 |
| 部門共通費 | 1,000 | 300 | 500 | 200 |
| 部門費 | 1,600 | 500 | 800 | 300 |
補助部門の配賦基準
| 補助部門 | 配賦基準 | A部門 | B部門 | C部門 |
| C部門 | 従業員数 | 8人 | 12人 | 2人 |
という内容であれば、まず補助部門であるC部門に配賦された製造間接費の300円は、
- A部門
- B部門
に配賦されます。
配賦基準が従業員数なので、それぞれの割合を掛けて配賦額を計算しましょう。
【A部門】
300円 × 8人 / 20人
= 300円 × 2/5
= 120円
【B部門】
300円 × 12人 / 20人
= 300円 × 3/5
= 180円
となり、まとめると以下の通りです。
製造間接費部門別配賦表
(単位:円)
| 合計 | A部門 | B部門 | C部門 | |
| 製造部門 | 製造部門 | 補助部門 | ||
| 部門個別費 | 600 | 200 | 300 | 100 |
| 部門共通費 | 1,000 | 300 | 500 | 200 |
| 部門費 | 1,600 | 500 | 800 | 300 |
| ∟ C部門費 | 300 | 120 | 180 | |
| 製造部門費 | 1,600 | 620 | 980 |
補助部門であるC部門に配賦された部門費を製造部門であるA部門・B部門に配賦しています。
そのため、製造部門費の合計額は、もともとの部門費の合計額と一致します。
相互配賦法による補助部門費の配賦
事務部門は、製造部門の従業員の分だけでなく、補助部門である修繕部門の従業員の給与計算もしていますね。
補助部門は製造部門だけでなく、ほかの補助部門に対してもサービスを提供しているということです。
相互配賦法では、この補助部門間のサービスのやり取りを考慮して2回配賦計算を行います。
製造間接費部門別配賦表
(単位:円)
| 合計 | 製造部門A | 製造部門B | 修繕部門 | 工場事務部門 | |
| 製造部門 | 製造部門 | 補助部門 | 補助部門 | ||
| 部門個別費 | 800 | 200 | 300 | 100 | 200 |
| 部門共通費 | 1,700 | 300 | 500 | 400 | 500 |
| 部門費 | 1,900 | 500 | 800 | 300 | 300 |
補助部門の配賦基準
| 補助部門 | 配賦基準 | 製造部門A | 製造部門B | 修繕部門 | 工場事務部門 |
| 修繕部門 | 修繕回数 | 3回 | 1回 | – | 2回 |
| 工場事務部門 | 従業員数 | 8人 | 12人 | 4人 | 2人 |
1回目の配賦計算では、自部門以外への部門へのサービスの提供割合により、補助部門費をほかの補助部門に配賦します。
これが「第1次配賦」です。
修繕部門費の配賦額
【製造部門A】
300円 × 3回 / 6回
= 300円 × 1/2
= 150円
【製造部門B】
300円 × 1回 / 6回
= 50円
【工場事務部門】
300円 × 2回 / 6回
= 300円 × 1/3
= 100円
工場事務部門費の配賦額
【製造部門A】
300円 × 8人 / 24人
= 300円 × 1/3
= 100円
【製造部門B】
300円 × 12人 / 24人
= 300円 × 1/2
= 150円
【修繕部門】
300円 × 4人 / 24人
= 300円 × 1/6
= 50円
製造間接費部門別配賦表
(単位:円)
| 合計 | 製造部門A | 製造部門B | 修繕部門 | 工場事務部門 | |
| 製造部門 | 製造部門 | 補助部門 | 補助部門 | ||
| 部門個別費 | 800 | 200 | 300 | 100 | 200 |
| 部門共通費 | 1,700 | 300 | 500 | 400 | 500 |
| 部門費 | 1,900 | 500 | 800 | 300 | 300 |
| 第1次配賦 | |||||
| ∟ 修繕部門費 | 300 | 150 | 50 | – | 100 |
| ∟ 工場事務部門費 | 300 | 100 | 150 | 50 | – |
補助部門の配賦基準
| 補助部門 | 配賦基準 | 製造部門A | 製造部門B | 修繕部門 | 工場事務部門 |
| 修繕部門 | 修繕回数 | 3回 | 1回 | – | 2回 |
| 工場事務部門 | 従業員数 | 8人 | 12人 | 4人 | 2人 |
2回目の配賦計算では、ほかの補助部門から配賦された補助部門費を製造部門のみに配賦します。
これが「第2次配賦」です。
第1次配賦で、修繕部門費として工場事務部門に100円・工場事務部門費として修繕部門に50円が配賦されていますね。
この100円・50円を製造部門A・製造部門Bに配賦します。
修繕部門費の配賦額
【製造部門A】
100円 × 3回 / 4回
= 75円
【製造部門B】
100円 × 1回 / 4回
= 25円
工場事務部門費の配賦額
【製造部門A】
50円 × 8人 / 20人
= 50円 × 2/5
= 20円
【製造部門B】
50円 × 12人 / 20人
= 50円 × 3/5
= 30円
製造間接費部門別配賦表
(単位:円)
| 合計 | 製造部門A | 製造部門B | 修繕部門 | 工場事務部門 | |
| 製造部門 | 製造部門 | 補助部門 | 補助部門 | ||
| 部門個別費 | 800 | 200 | 300 | 100 | 200 |
| 部門共通費 | 1,700 | 300 | 500 | 400 | 500 |
| 部門費 | 1,900 | 500 | 800 | 300 | 300 |
| 第1次配賦 | |||||
| ∟ 修繕部門費 | 300 | 150 | 50 | – | 100 |
| ∟ 工場事務部門費 | 300 | 100 | 150 | 50 | – |
| 第2次配賦 | 50 | 100 | |||
| ∟ 修繕部門費 | 100 | 75 | 25 | ||
| ∟ 工場事務部門費 | 50 | 20 | 30 | ||
| 製造部門費 | 1,900 | 845 | 1,055 |
製造部門費は、
- もともとの部門費
- 第1次配賦の合計額
- 第2次配賦の合計額
を足した金額です。
もともとの部門費の合計額と製造部門費の合計額は、一致します。
製造部門費を各製造指示書に配賦するときは、どう処理する?
製造間接費部門別配賦表
(単位:円)
| A製造部門 | B製造部門 | 合計 | |
| 製造部門費 | 4,500 | 3,000 | 4,500 |
当月の直接作業時間
| 製品No.1 | 製品No.2 | 合計 | |
| A製造部門 | 12時間 | 18時間 | 30時間 |
| B製造部門 | 6時間 | 9時間 | 15時間 |
各製造指図書への配賦額を計算していきます。
【A製造部門費の配賦率】
4,500円 ÷ 30時間 = @150円
【B製造部門費の配賦率】
3,000円 ÷ 15時間 = @200円
この配賦率に配賦基準(今回は、直接作業時間)を掛けて計算していきます。
| 製品No.1 | 製品No.2 | |
| A製造部門 | @150円 ×12時間 = 1,800円 | @150円 × 18時間 = 2,700円 |
| B製造部門 | @200円 × 6時間 = 1,200円 | @200円 × 9時間 = 1,800円 |
| 合計 | 3,000円 | 4,500円 |
部門別予定配賦率は、どうやって決定する?
製造部門費を予定配賦するためには、期首の時点で1年間の製造部門ごとの予算額を見積もります。
これが「各製造部門費予算額」です。
また、「基準操業度」という数値も必要になります。
配賦基準を直接作業時間としている場合であれば、1年間に予定されている直接作業時間の合計値が基準操業度です。
予定配賦率は、各製造部門費予算額を基準操業度で割ることで求められます。


| A製造部門 | B製造部門 | 合計 | |
| 製造部門予算額 | 15,000円 | 9,000円 | 24,000円 |
| 直接作業時間(予定) | 300時間 | 120時間 | 420時間 |
今回、基準操業度となるのは、直接作業時間です。
【A製造部門】
15,000円 ÷ 300時間 = @50円
【B製造部門】
9,000円 ÷ 120時間 = @75円
がそれぞれの予定配賦率となるので、当月の実際直接作業時間が
| 製品No.1 | 製品No.2 | 合計 | |
| A製造部門 | 15時間 | 12時間 | 27時間 |
| B製造部門 | 10時間 | 9時間 | 19時間 |
であれば、部門別予定配賦額は、
| 製品No.1 | 製品No.2 | |
| A製造部門 | @50円 × 15時間 = 750円 | @50円 × 12時間 = 600円 |
| B製造部門 | @75円 × 10時間 = 750円 | @75円 × 9時間 = 675円 |
| 合計 | 1,500円 | 1,275円 |
となります。
製造部門費を予定配賦しているときは、月末はどのような処理になる?
A製造部門費が
- 予定配賦額 → 1,500円
- 実際発生額 → 1,200円
の場合、300円の製造部門費配賦差異があり、足は出ていませんね。
この場合の仕訳は、
| 借方 | 貸方 | ||
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 製造部門費配賦差異 | 300 | A製造部門費 | 300 |
となります。
また、B製造部門費が
- 予定配賦額 → 1,500円
- 実際発生額 → 1,600円
の場合、100円の製造部門費配賦差異があり、足が出ていますね。
この場合の仕訳は、
| 借方 | 貸方 | ||
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| B製造部門費 | 100 | 製造部門費配賦差異 | 100 |
となります。
最後に



いかがでしたか…?
小難しい用語がいくつか出てきましたが、漢字の意味そのままなので、そこまで身構える必要はありません。
「個別原価計算」と被る内容が多いので、ぜひセットにして解き方を覚えていってください。
丸暗記してしまうレベルまで読み込んで、得意分野にしていきましょう!