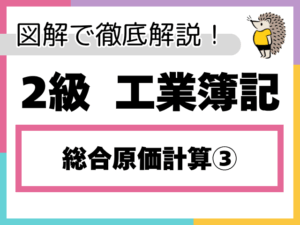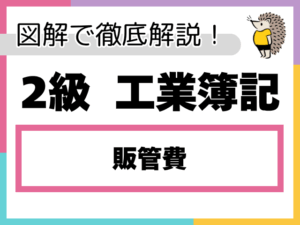はりねずみ
はりねずみ材料費の予定価格法について、解説していきます!
簿記2級の工業簿記学習における原価計算の中でも大きな割合を占めるのが材料費です。
材料費の計算を正確に行うことは、製品原価を算定し、経営判断に役立てる上で非常に重要になります。
特に、簿記2級で新しく学習する「予定価格法」や「材料消費価格差異」、そして「材料副費」の扱いは、多くの受験生が苦手とするところです。
この記事では、これらの重要論点を独学者にもわかりやすく解説します。
材料費の基本 – 消費単価計算をマスターしよう
材料費は、製造活動で使用された材料の原価です。
その金額は、使用した材料の「数量」と「単価」を把握することで計算されます。
消費数量は、材料の受入れや払い出しの記録(継続記録法)や、期末の実地棚卸数量から計算する方法(棚卸計算法)によって把握されます。
問題となるのは、材料の消費単価です。
同じ種類の材料でも、仕入先や時期によって購入単価が異なることがよくあります。
そのため、払い出された材料がいくらで仕入れたものなのかを把握し、適切な単価で消費額を計算する必要があります。
この考え方は、簿記3級で学習した商品の払い出し単価の計算と同じです。
消費単価の主な計算方法
簿記2級の工業簿記では、材料の消費単価計算において、主に以下の3つの方法が登場します。
これらはすべて、実際に仕入れた単価(実際単価)を用いて計算する方法です。


| 先入先出法 (さきいれさきだしほう) | 先に仕入れた材料から先に払い出されたと仮定して計算する方法です。 古い単価の材料から順に消費されたと考えるため、直感的に分かりやすい方法と言えます。 物価が変動する場合、この方法で計算された消費額は、実際にかかったであろう最新の単価とはずれが生じる可能性があります。 |
|---|---|
| 移動平均法 (いどうへいきんほう) | 材料を仕入れる都度、それまでの残高と新しく仕入れた材料の合計金額を合計数量で割り、その時点での平均単価を計算する方法です。 仕入れがあるたびに平均単価が更新されるため、「移動」平均法と呼ばれます。 計算の手間はやや多いですが、常に最新の平均単価で消費額を計算できます。 |
| 総平均法 (そうへいきんほう) | 一定期間(通常は1ヶ月)の期首棚卸高と当月仕入高の合計を、期首棚卸数量と当月仕入数量の合計で割って、期間全体の平均単価を計算する方法です。 計算は期間に一度で済みますが、期間の終わり(月末)にならないと平均単価が確定しないため、月中の材料消費の計算には向かないというデメリットがあります。 |
これらの方法のどれを選ぶかによって、計算される材料の消費額や期末の材料在庫額は異なります。
また、これらの単価計算方法は、あくまで会計上の計算ルールであり、実際に倉庫でどの材料から払い出されているかという物理的な流れとは直接関係ありません。
簿記2級の重要論点 – 予定価格法と材料消費価格差異
先入先出法や平均法といった実際単価を使った計算方法は、単価の把握や計算に手間や時間がかかる場合があります。
特に総平均法のように、月末まで単価が確定しない方法では、日々の迅速な原価計算が困難になります。
予定価格法とは?なぜ必要なのか
そこで、簿記2級工業簿記で非常に重要になるのが「予定価格法」です。
予定価格法とは、材料の消費単価を、あらかじめ定めた「予定消費単価」を用いて計算する方法です。
この方法を用いることで、月中の材料消費時においては、実際の仕入れ単価を確認する手間を省き、迅速に原価計算を進めることが可能になります。
なお、ここでいう予定消費単価は、あくまで過去の実績などを基に「通常の単価」として見込まれる金額であり、標準原価計算で用いる「理想的な単価(標準値)」とは区別されます。
予定価格法における材料の消費額(予定消費額)は、以下の式で計算されます。


予定消費額
= 予定消費単価 × 実際消費数量
重要なのは、単価は予定を用いますが、数量は実際に消費した数量を用いるという点です。
材料消費価格差異の計算
予定価格法では、月中の処理を予定単価で行いますが、月末には実際の材料単価が判明します。
そこで、月末に、実際に発生した単価で計算した消費額(実際消費額)と、月中に予定単価で計算した予定消費額との間に生じた差額を把握し、修正する必要があります。
この差額を「材料消費価格差異(ざいりょうしょうひかかくさい)」と呼びます。
材料消費価格差異は、以下の式で計算されます。
材料消費価格差異
= 実際消費額 - 予定消費額
もし計算結果がプラス(実際 > 予定)であれば、予定よりも実際にかかった費用が多かったことになり、「不利差異(ふりさい)」となります。
逆にマイナス(実際 < 予定)であれば、予定より実際が少なくて済んだことになり、「有利差異(ゆうりさい)」となります。
差異の仕訳と決算整理


月中に材料を消費した際には、上記の「予定消費額」で計算し、直接消費であれば仕掛品勘定へ、間接消費であれば製造間接費勘定へ振り替える仕訳を行います。
そして月末に材料消費価格差異を計算し、以下のように仕訳で処理します。
5円の不利差異が発生した場合、予定より費用が多くかかったため、材料勘定を減らし、差異として計上します。
| 借方 | 貸方 | ||
| 材料消費価格差異 | 5 | 材料 | 5 |
10円の有利差異が発生した場合、予定より費用が少なくて済んだため、材料勘定を戻し、差異として計上します。
| 借方 | 貸方 | ||
| 材料 | 10 | 材料消費価格差異 | 10 |
この「材料消費価格差異」勘定には、毎月発生した差異の金額が集計されていきます。
そして、会計期間の終わりである決算時には、この材料消費価格差異勘定の残高をゼロにする処理を行います。
原則として、この差異は売上原価に振り替えられます。
材料副費の落とし穴!?取得原価への算入ルール
材料費は、単に材料の購入代価だけでなく、それ以外にかかる「付随費用」も含めて計算する必要があります。
これらの付随費用を「材料副費(ざいりょうふくひ)」と呼びます。
材料副費は、原則として材料の取得原価に含めることになります。
材料副費の種類と取得原価算入
材料副費は、発生するタイミングによって「外部副費」と「内部副費」に分けられます。


| 外部副費 | 材料を仕入れて、自社の倉庫に受け入れるまでに発生する費用です。 例えば、引取運賃や関税などがあります。 外部副費は、原則として材料の取得原価に含める必要があります。 (金額が少額な場合は含めない場合もあります。) |
|---|---|
| 内部副費 | 材料が自社の倉庫に受け入れられてから、製造工程に投入されるまでの間に発生する費用です。 例えば、検収費用や倉庫保管料などがあります。 内部副費については、外部副費とは異なり、取得原価に含めても、含めなくてもどちらでも良いという任意での処理が認められています。 一部のみを含めることも可能です。 これは、内部副費を個々の材料に正確に按分・集計することが難しい場合があるためです。 |
材料の取得原価は、
購入代価 + 外部副費 + 内部副費
となりますが、内部副費を含めるかどうかは会社の判断に委ねられているという点を押さえましょう。
内部副費の予定配賦と差異処理
内部副費の実際発生額が、すぐに分からないことがあります。
そのため、材料消費価格と同様に、内部副費についても「予定配賦」を行う場合があります。
予定配賦とは、あらかじめ定めた基準(例えば購入代価の●%など)に基づいて、内部副費を材料の取得原価に含める方法です。
材料を仕入れた際に、この予定配布額を含めて取得原価を計算する仕訳を行います。
内部副費を予定配賦した場合、後日判明する実際発生額と予定配賦額との間に差異が生じます。
この差異を「材料副費配賦差異(ざいりょうふくひはいふさい)」と呼びます。
この材料副費配賦差異も、材料消費価格差異と同様に、最終的には売上原価に振り替えられるのが一般的です。
例えば、内部副費の予定配賦額が100円・実際発生額が150円で、50円の不利差異が発生した場合の仕訳は、以下の通りです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 材料副費配賦差異 | 50 | 材料副費 | 50 |
まとめ
簿記2級の工業簿記における材料費計算では、様々な単価計算方法、特に予定価格法とその差異処理が重要な論点となります。
材料消費価格差異は、ボックス図を活用して計算と有利・不利の判断をスムーズに行えるように練習しましょう。
また、材料副費の外部副費と内部副費の区別や、内部副費の取得原価算入の任意性、そして予定配布した場合の差異処理についても理解しておくことが大切です。
これらの論点は、独学での合格を目指す上で必ずマスターしておくべきポイントです。
繰り返し練習し、自信を持って本試験に臨めるように頑張りましょう!